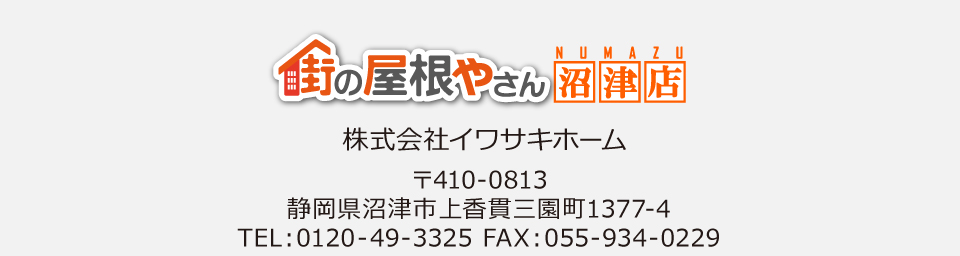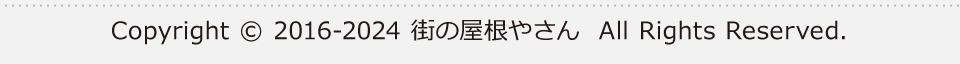2025.10.23
部分葺きかえで屋根下地も新たに! 伊豆市にお住まいのみなさま、こんにちは。街の屋根やさん沼津店です。今日の現場ブログは前回に引き続き、強風で水切り板金が剥がれ、軒先の部分葺き替え工事を実施することになった伊豆市のお客様宅での屋根工事の様子をお届けします!※前回の現場ブログ:伊豆市…

屋根の一番高い部分、左右の屋根面が交わる「棟(むね)」と呼ばれる場所をご存じでしょうか?
この棟は、屋根全体の中でも特に重要な部分で、降った雨水はここを境に右と左へと流れていきます。
まるで人生の岐路のように…と、つい感じてしまいます(少し話が逸れましたね)。
棟には、通常の屋根瓦とは異なる施工方法が使われています。
棟部分の仕上げに使われるのが「棟瓦(むねがわら)」や「のし瓦」といった専用の瓦です。
これらをしっかり固定することで、雨や風から家を守る屋根の耐久性を保っているのです。

棟瓦をめくると、中からは「葺き土(ふきつち)」と呼ばれる粘土質の土が現れます。
これは、棟瓦を安定させるために古くから使われてきた工法で、瓦の間を支えるクッションのような役割をしています。
しかし、年月が経つとこの葺き土にヒビが入ったり、崩れてきたりします。
原因は、風雨や地震などの外的な衝撃。また、自然乾燥による収縮も影響します。
こうした劣化が進むと、上に乗っている棟瓦やのし瓦にもズレやゆがみが出始め、最悪の場合は崩れ落ちてしまう危険性もあるのです。
特に、雨漏りの原因になりやすいのがこの棟部分。
見た目にはわかりづらくても、内部でじわじわと症状が進行していることが少なくありません。

一般的に、棟の改修工事は20年に一度が目安とされています。
放置してしまうと、瓦が波打って見えたり、落下の危険も。早めの点検と対処で、お住まいを長く安心して使うことができます。
今回の施工では、古いのし瓦・棟瓦・葺き土をすべて取り除いたあと、白セメントを使って新しい土台を作り直しました。
この白セメントは、「面戸(めんど)」と呼ばれる隙間埋めの役割も果たします。
蒲鉾型(かまぼこがた)に形を整えながら、水平・高さを丁寧に調整し、最後に新しいのし瓦と棟瓦をしっかりと積み上げて完了です。

近年では、施工に使用する材料も大きく進化しています。
セメントや接着剤などは、固まっても“しなやかな弾力”を持つ素材が多く、地震などの振動が加わっても、ヒビ割れしにくくなっています。
長く安心してお住まいになれるよう、日々研究と改良が進められているんですね。

私共では、地元沼津を中心に、三島、裾野、長泉、清水町、函南町、伊豆の国で安心安全大満足リフォーム&屋根外壁外回り&新築住宅を施工していきます。
お住まいのご相談はお気軽にご連絡ください。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん沼津店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.