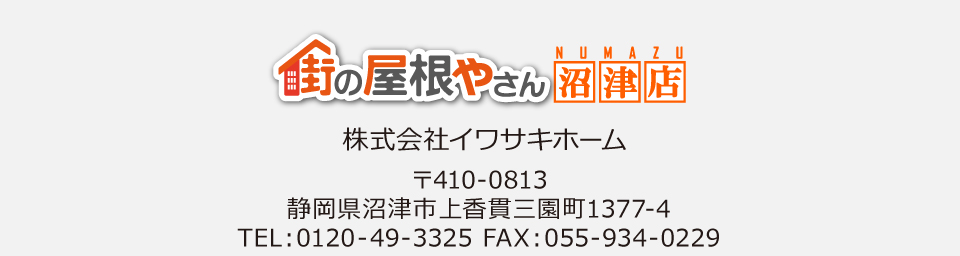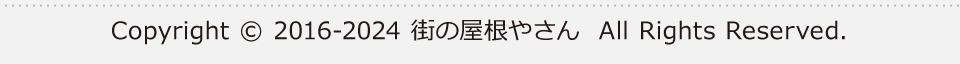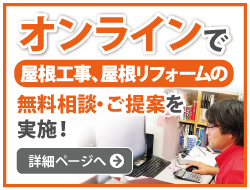
沼津市にて、築60年以上は経っている瓦屋根の棟(むね)部分の補修工事を行いました。
施主様からは、「もしかすると70年以上前、小学生の頃にはもう建っていたかもしれない」とのお話もあり、とても思い入れの深いご自宅であることが伝わってきました。
長年、地域に根ざしたお住まいは、瓦屋根業者による点検や簡易的なメンテナンスが何度か行われてきたそうですが、やはり60〜70年という長い年月の中で、徐々に劣化が進んでいる部分も見られました。
今回補修が必要だったのは、屋根の一番高い部分「棟(むね)」の部分です。
棟瓦は、屋根の接合部にある重要な部分で、雨風から家を守る役割を果たしています。
特に、のし瓦と呼ばれる平らな瓦を何段も積み重ねて作られているこの棟部分では、それらを固定していた「葺き土(ふきつち)」と呼ばれる粘土が長年の風雨や気温変化で風化し、ポロポロと崩れ始めていました。
また、棟の隙間から雨水が入り込む可能性もあり、雨漏りの危険性も高まっていたため、早急な対応が必要な状況でした。


今回は棟瓦の安全性と耐久性を高めるため、以下の工程で補修を行いました。
1.風化した古い粘土の撤去
まずは劣化した粘土をすべて丁寧に取り除きました。
2.棟の基礎を白セメントで新しく作成
白セメントとは、強度と防水性に優れた建材で、瓦の基礎をしっかりと固定するのに最適です。
3.のし瓦を3段積み重ねる
のし瓦は棟に積み上げていく平たい瓦で、しっかりとバランスをとりながら、丁寧に重ねていきました。
4.銅線での固定処理
耐久性をさらに高めるため、のし瓦の基礎に銅線を一定間隔で埋め込み、上に向けて通しておきます。
5.棟瓦を伏せ、銅線を通す
棟瓦には穴が空いており、そこに先ほどの銅線を通して、しっかりと瓦を固定します。
6.銅線の先端を“コブ”にして固定完了
最後に銅線の端を大きな“コブ”状にして、棟瓦が抜け落ちるのを防ぎます。
これで、強風や地震にも耐えられる丈夫な棟が完成です。


昔は「古くなったら壊して建て直す」という考え方が主流でしたが、今の時代は違います。
限りある資源を大切にし、長く住み続けるために「修理・補修・リフォーム」で対応するのが一般的です。
今回のように、部分的に劣化している箇所を早めに直すことで、家全体の寿命をぐっと延ばすことができます。
私共では、地元沼津を中心に、三島、裾野、長泉、清水町、函南町、伊豆の国で安心安全大満足リフォーム&屋根外壁外回り&新築住宅を施工していきます。
お住まいのご相談はお気軽にご連絡ください。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん沼津店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.